
 Chap.2
ラダー図シーケンス図を書く
Chap.2
ラダー図シーケンス図を書く

 Chap.2
ラダー図シーケンス図を書く
Chap.2
ラダー図シーケンス図を書く
この章では、簡単なラダー図シーケンス図を書いてみます。
2.1 母線を引く
まず図面の左右両端に縦線を並行に書きます。(図2.1) この線は母線といって、電圧が印加されていますが、電源や直流電源の記号は普通省略します。
仮に左右の母線に電圧計を当てると、交流の200Vとか直流の24Vに針が振れると考えてください。
 |
これで、ラダー図シーケンス図を書く準備ができました。
2.2 回路図を書く
では、左右の母線間に1行回路を書いてみましょう。(図2.2)
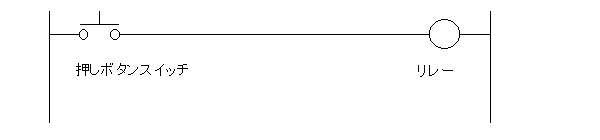 |
この回路は、a接点の押ボタンスイッチとリレーのコイルが直列に接続されています。
押ボタンスイッチを押さないときは、リレーのコイルには電流は流れませんが、押ボタンスイッチを押すと、左右の母線間に電圧が印加されているためリレーのコイルに電流が流れます。
では、もう1行左右の母線間に回路を書いてみましょう。(図2.3)
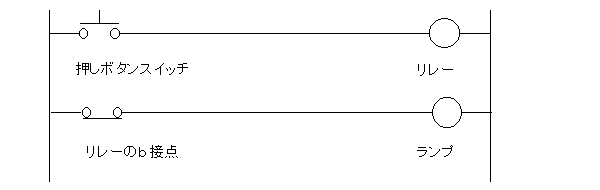 |
2行目の回路は、1行目で使ったリレーのb接点とランプ(とりあえず白熱電球と考えてください)が直列に接続されています。
押ボタンスイッチを押さないときは、リレーのコイルには電流は流れませんから、
リレーのb接点は導通状態でランプは点灯します。
押ボタンスイッチを押したときは、リレーのコイルに電流が流れ、リレーのb接点は非導通状態となりランプが消灯します。
つまり、このラダー図シーケンス図は、押ボタンスイッチを押したときランプを消す制御をおこなっています。
図2.3のラダー図シーケンス図の1行目のリレーのコイルと、2行目のリレーのb接点は1つの部品です。
このようにリレーのコイルと接点は同一の行に書く必要はありません。
その代わり、離れた場所に書いたリレーのコイルと接点が同じ1つの部品であることを示すために、リレーに記号を付けます。
これで、ラダー図シーケンス図上は離れていても同じ記号であれば1つの部品とわかるわけです。